![]()
| メインメニュー | よくあるご質問 | イソバンドって何? | 会社概要 | リ ン ク | 施工例写真 | お問合せ |
著者:矢崎 光彦
道元ワールド 12 「同事」(人のよろこびは我がよろこび)
 2009.7.26
2009.7.26
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
同事というは不違なり、自にも不違なり、佗にも不違なり、譬えば人間の如来は人間に同ぜるが如し、佗をして自に同ぜしめて後に自をして侘に同ぜしむる道理あるべし、自侘は時に随うて無窮なり、海の水を辞せざるは同時なり、是故に能く水聚りて海となるなり。 (修証義)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「修証義」の第24節の言葉です。「修証義」とは、大内青巒居士が、明治の時代に「正法眼蔵」のエキスをまとめられたものです。言わば、「正法眼蔵」のダイジェスト版です。第1章「総序」、第2章「懺悔滅罪」、第3章「受戒入位」、第4章「発願利生」、第5章「行持報恩」の5章から構成されています。第4章「発願利生」には、「布施」「愛語」「利生」「同事」の四つが、述べられています。「利生」とは、仏が衆生を利益するという意味です。「利益」は「りえき」ではなく、「りやく」と読みます。他人を益することです。ちなみに、自分を益することは、功徳と呼んでいます。「発願利生」とは、他人を益そうと誓願をおこすことです。私たちのことに当てはめてみると、社会生活を営んでいく上で大切な四つの項目ということです。「愛語」については、以前述べましたので、今回は、「同事」についてまとめてみたいと思います。
「同事というは不違なり、自にも不違なり、佗にも不違なり、」
同事ということは、区別や差別をつけないことです。自分に対しても他人に対しても区別や差別をしない。逆に言うと、自分を認め、他人を認める。カール・ロジャーズのカウンセラーの必要にして十分な条件の受容・共感・自己一致に通じるところがあります。他人を認めるは、「受容・共感」、自分を認めるは、「自己一致」です。「自にも不違なり、他にも不違なり」は、「受容・共感・自己一致」といってもいいかと思います。
「譬えば人間の如来は人間に同ぜるが如し、」
「同事」の一つ目の比喩です。「同事」とは、釈尊が人間の姿をして人を導かれたようなことであるとしています。
「佗をして自に同ぜしめて後に自をして侘に同ぜしむる道理あるべし、」
「同事」には順番があります。「佗(他)をして自に同ぜしめ」とは、私はあなたを理解しますということです。相手の思いを十分に理解し、こちらの思いもわかってもらう。この一体感こそ道理にかなっている。まず、他の言い分をよく聞き理解して吸収し、心開いた相手にさせてから、自分を開いて入れていく。
「自侘は時に随うて無窮なり、」
「無窮」とは窮まりがないこと、つまり自分と他人は常に相互関係にあるということ。だから、時に応じて自分を他人に従わしめることもあり、逆に他人を自分に従わしめることもある。しかし他に従うことは、自分に背くのでもなく、他人が自分に従うのも他人が他人にそむくことでもない。
「海の水を辞せざるは同事なり、是故に能く水聚りて海となるなり。」
「同事」の二つ目の喩えです。海はたくさんの川の水を受け入れる。受け入れてもらえるから水も自然と集まって海になります。仏教的に言うと海は無我であって、色々な川の水を受け入れる。色々な川の水も無我であれば無我の大海と自然と融合していく。ですから、同事とは、無我の世界をいっていることでもあります。
禅には、「自他一如」という言葉があります。自と他は一つが如し、つまり自分と他人は、同じことであって区別するものではない、ということです。カウンセリングでは、「相手の立場に立って」という姿勢を大切にします。この姿勢の究極が「同事」ということになると思います。
ところで、載せた写真は、宮古島で撮ったものです。ラッキーなことに宮古島に仕事があり、2週間前に行ってきました。宮古島トライアスロンの出発点の海岸から海を撮ったものです。宮古島はサンゴ礁から出来た島ということで、砂浜が真っ白です。白い砂浜と、エメラルドグリーンの浅い海、コバルトブルーの沖合い。私が見た中では最も美しい海だと思います。ただがっかりしたのは、ペットボトルがところどころに転がっていたことです。美しい砂浜にペットボトルが転がっているのはどうも似合いません。
道元ワールド14 「利行」(人のよろこびは我がよろこび) 2010.01.03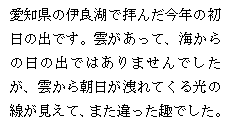

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
利行というは貴賎の衆生に於きて利益の善巧を廻らすなり、窮亀を見、病雀を見しとき、彼が報謝を求めず、唯単えに利行に催おさるるなり、愚人謂わくは利佗を先とせば自らが利省かれぬべしと、爾には非ざるなり、利行は一法なり、普く自侘を利するなり。
(正法眼蔵 菩提薩埵四摂法)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「愛語」「同事」「布施」と四摂法のうち三つまで見てきました。今回は最後の「利行」です。
「利行というは貴賎の衆生に於きて利益の善巧を廻らすなり、」
「利行」とは、「利他行」のことで、他のために尽力することです。「利益」とは、仏の教えに従って行動することによって得られる恩恵や救済のことです。「善巧」とは、「善巧方便」のことで、臨機応変に色々巧みな方法によって人を導くことです。
「窮亀を見、病雀を見しとき、彼が報謝を求めず、唯単えに利行に催おさるるなり」
「窮亀」と「病雀」は、「蒙求」という漢籍の故事に倣っています。晋の孔愉は、子供にいじめられている亀を買い取って川に放してあげた。後漢の揚宝は、フクロウにいじめられ傷ついた雀を助けてあげた。この亀や雀は後に恩返しをして孔愉も揚宝も孫の代まで栄えたということです。窮亀や病雀を救った報酬などを求める心を考えず利行の心からなされたものであったからこそ、報恩感謝が現れたのです。
「愚人謂わくは利佗を先とせば自らが利省かれぬべしと、爾には非ざるなり、」
愚かな人は、人助けを先にすれば、自分は損をするにちがいないと考えてしまいますが、そうではないのです。
「利行は一法なり、普く自侘を利するなり。」
仏教では、「自他不二」といいます。自分と他の人は別々のものではない。ですから、他のためになることは必ず自分のためにもなり、自分のためになることは必ず他のためにもなるのです。
よくGive&Takeといいますが、Takeが目的で、Giveするのであれば、利行にはなりません。Takeを放棄したGiveが利行です。困った人がいれば何とかしてあげたくなるのが人情です。ただ、お礼を期待したり、助けてあげたんだという自尊心があると利行ではなくなってしまいます。
宮澤賢治は法華経の精神で生き抜いた人といわれていますが、有名な「雨ニモマケズ」は、利行のこころを表したものと言ってもいいと思います。「雨ニモマケズ」の詩は、皆さんご存知だと思いますので、パロディ版を作ってみました。
雨にも負けて 風にも負けて 雪にも夏の暑さにも負ける
ひ弱な身体を持ち そのくせ欲は強く
しょっちゅう怒り いつもイライラしている
食事はインスタント食品で済ませ
あらゆることに自分が一番で
勉強なんかもってのほか
そして何も覚えていない
ゴミだらけの部屋にとじこもり
東に病気の子供あれば 勝手に病気になったんだろと言い
西に疲れた母あれば 養老院へ行けと言い
南に死にそうな人あれば もう寿命だと言い
北に喧嘩や訴訟があれば もっとやれとけしかける
夏は冷房をガンガンつけ
冬は暖房をガンガンつける
みんなに「なんてやつだ」と言われ
叱られもせず どうでもいいと思われる
そんな私に 誰がした
作ってみると、自分に当てはまることも少なからずあり、「利行」にはまだまだかなと思った次第です。
| メインメニュー | よくあるご質問 | イソバンドって何? | 会社概要 | リ ン ク | 施工例写真 | お問合せ |